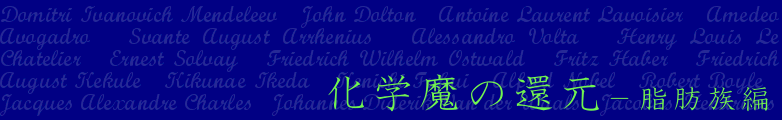分類法には
1.炭素数による分類
2.ヒドロキシル基による分類
3.OHがついているCによる分類
の3種類がありますが、3番目が特に重要です。それと同時に、1.2.と比べると分かりにくい分類法のようです。注意して読んでください。
1.炭素数による分類
CH3OHやC2H5OHのように炭素数が少ないアルコールを低級アルコール、C10H21OHやC12H25OHのように炭素数が多いアルコールを高級アルコールといいます。
普通はC6以上が高級に分類されますね。
これは水への溶解度と関係があります。
アルキル基は水になじまないんですが、ヒドロキシル基は水と仲が良いんです。そのため、低級アルコールは水に溶けやすく、炭素数が増すにつれて溶解度は小さくなります。
このように1つに分子の中でも、水に対して馴染みやすい部分と馴染みにくい部分があることがあります。水と仲が良い部分を親水基、仲が悪い部分を疎水基といいます。
親水基:極性を持ち水和しやすい部分
疎水基:無極性で水和されにくい部分
2.ヒドロキシル基による分類
分子中のヒドロキシル基の数を「アルコールの価数」といいます。ヒドロキシル基が1個あるものを1価アルコール、ヒドロキシル基が2個あるものを2価アルコール、3個あるものを3価アルコールといいます。
また2価以上のアルコールを多価アルコールといいます。
アルコールの価数も溶解度に影響します。多価アルコールの方が水に溶けやすいですね。ヒドロキシル基は親水基になるので、多いほうが溶けやすいです。
これも特には問題ないでしょう。
3.OHがついているCによる分類
表題を見ただけでは分かりにくいと思いますが、ゆっくりと見ていってください。
まずは3−メチル−1−ブタノールを考えてみます。
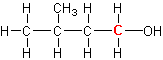
さて、炭素Cは4つの原子と結合することが出来ます。この場合の赤いCは、1つのC、2つのH、そしてOHと結合しています。
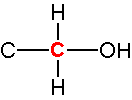
赤Cを中心に拡大
この場合、1つの炭素と結合しているので、3−メチル−1−ブタノールは第一級アルコールといいます。
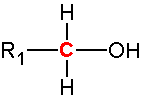
第一級アルコール
次に3−メチル−2−ブタノールを考えてみます。
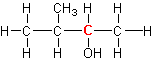
さて、今度着目する炭素は右から2番目ですね。この赤いCは、2つのC、1つのH、そしてOHと結合しています。
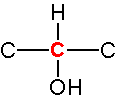
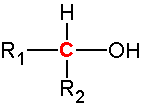
第二級アルコール
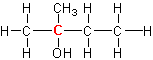
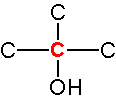
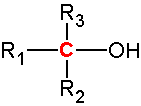
第三級アルコール
このようにヒドロキシル基が結合している炭素原子に、他の炭素原子が何個結合しているかによって分類し、
0個または1個のときを第一級アルコール
2個のときを第二級アルコール
3個のときを第三級アルコール
といいます。
(メタノールCH3OHは、第0級という新しい分類を作らずに、第一級アルコールに含めます。)
ところで、第一級、第二級、第三級と見てきたとき、赤いCの周辺を抜き出して考えてきましたが、もっと簡単に、ヒドロキシル基の位置だけで判別することが可能です。
もう一度3つのアルコールを見てみます。
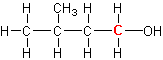
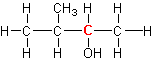
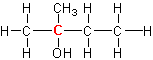
3−メチル−1−ブタノール;3−メチル−2−ブタノール;2−メチル−2−ブタノール
(第一級) (第二級) (第三級)
ヒドロキシル基の位置に着目してください。主鎖の一番端っこにOHがあるときは、第一級
主鎖の途中にOHがあるときは、第二級
側鎖の枝分かれ部分にOHがあるときは、第三級
ということが出来ます。
これらは単なる位置異性体・構造異性体というだけではなくて、反応性に大きな違いが見られます。この違いは赤いCに付いている水素の数から来るものですが、詳しくは後で記述します。